魅力的なキャラクターの作り方!2つのステップを実例付きで解説
透明.png)
やあ、葵です。(@Aoi_Yamato_100)
魅力的なキャラクターが作りたいけどどうにもしっくりこない。
本記事ではそんな悩みを持った人のために、「魅力的なキャラクターってどんなもの?」という説明から、「実際に作るときはどうすればいいの?」という疑問についても解説します。
良いキャラクターというのは、もはや小説にかぎらず、アニメやマンガ、ドラマから映画にいたるまで、物語であればどんな媒体であっても重要となる要素ですよね。
キャラクターがよければ物語は自然と進むものです。
ですので、ストーリー作りに悩んでいる人もぜひ参考にしてみてください。
- 魅力的なキャラクターが作りたい
- キャラクターの作り方の基本が知りたい
- 参考になるような実例が知りたい
魅力的なキャラクターとは

結論からいうと、魅力的なキャラクターとは、
- 動機がしっかりしている
- その動機の背景がちゃんとある
のことです。
こういうキャラクターは、作中でそのキャラクター性がブレることはありませんし、読者から見てもその実像がハッキリと認識できます。
このキャラクター性がブレまくると、読者はそのキャラクターがどういう人物であるかがうまく認識できず、いつまでたっても感情移入や共感ができない状態になってしまいます。
もし、自分の作ったキャラクターにいまいちしっくりこないという人は、次のことを意識してみてください。
キャラクターの動機(欲求)はなにか
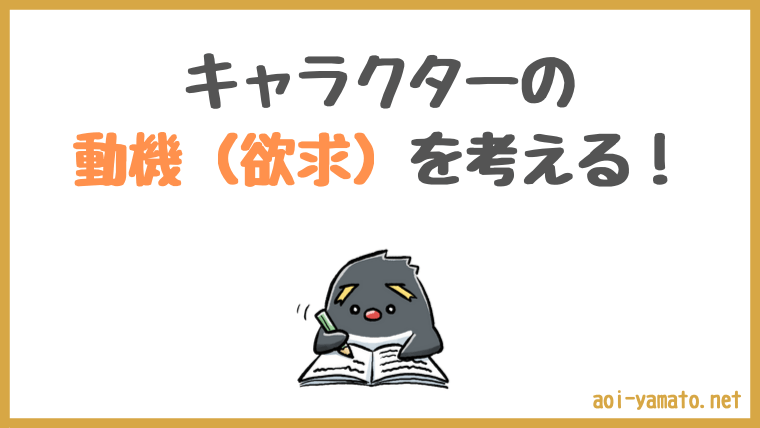
人間にはさまざまな欲求があります。
そして欲求は、そのままその人間が動く理由=動機になります。
- 大金を得たい
- かわいい女の子と出会いたい
- 偉くなりたい
近頃のネット小説では『スローライフを送りたい』というものも多いです。
現実がせわしなく大変なことの反動化もしれないね。
ともあれ、現実で満たせない自分の欲求を作中で満たそうとするキャラクターは、感情移入先/共感先としてとても強い引力を持ちます。
キャラクターたちが持つ欲求が、読む側の欲求と重なったとき、彼らがどういうふうにその欲求を満たすため動くのか、読者はじっと観察することでしょう。
- 「ああ、そうだよな、おれもそうする」
- 「そうそう、その選択はわかるわ」
そしてそのキャラクターの行動が、読者の共感を誘ったとき、彼らは親しみやすさという最強の武器を得るのです。
親しみやすさを持つキャラクターは魅力的
親しみやすさを持つキャラクターは、本当にそこにいるかのような実像を感じることができます。
自分の傍にいて、同じ思いを持って困難に立ち向かっているキャラクターは、応援したくなりますよね。
逆に、動機もなく、それゆえに親しみやすさも持てないキャラクターの場合、当然ながら読者は彼らに魅力を感じません。
しかも動機がないので物語は進まないし、動機があったとしてもそれが安定しなければ物語は進む先がころころ変わって安定しません。
動機がないキャラクターが主人公だとどうなる?
仮に、動機がまるでないキャラクターが主人公だった場合、物語がどうなるのかを考えてみましょう。
- ヒロイン:「冒険に出ようよ!」
- 主人公:「え、別にいいや。俺は部屋にいるよ」
- 王様:「敵国が攻めてきた!」
- 主人公:「そういうこともあるよね。俺は別にどうでもいいから寝る」
- 神様:「あなたの余命はあと一年です……」
- 主人公:「そっか。しょうがないね。でもやりたいことないからいいや」
なにもはじまらない。
これらの選択になんらかの理由があるのであればまだしも、単純になにかをする気力がない主人公というのは実にクセモノです。
これでちゃんとした物語が作れる人は、たぶんこの記事を見なくても十分おもしろい作品が書ける人でしょう。
だから動機をちゃんと作っておく
初心者の方は、まずなんらかの目的や動機があって、そのために動くことができる主人公を作ってください。
そこがしっかりしていればストーリーはおのずと進むようになります。
そしてストーリーが進み、物語上の選択がいくつも重なれば、キャラクターたちの動機が読者にもわかる形で表れてきます。
その動機、欲求が読者のそれと一致したとき、読者はそのキャラクターに大きな魅力を感じることになるでしょう。
キャラクターの動機の「背景」を考える

キャラクターの動機には、必ず背景を設定するべきです。
「なんとなく好きだから」という理由が悪いわけではありませんが、キャラクターの個性の軸となるような動機に背景がないと、いざというときに彼らが迷うことになってしまいます。
- 物語の途中でもっと魅力的な欲求を見つけた
- 価値観を揺さぶられるような出来事が起こった
その価値観の変化を描きたいのであればもちろんそれはかまいません。
しかし、キャラクターの個性の軸となるような動機の変化は、読者を混乱させます。
そのキャラクターがどんなキャラクターなのかまだ固まっていない物語の序盤でやるべきではありませんし、仮にやるにしても、そのキャラクターの今までの個性に共感していた読者は、一気に離れてしまうことも覚悟しなければなりません。
透明.png)
正直、こういったキャラクターの価値観の変化は、大きなエピソードの最後にやるくらいでちょうどいいレベル。それこそ、その価値観の変化を物語のテーマにするくらいでないと悪影響をおよぼす。
だから、ちょっとやそっとのことではそのキャラクターの動機が変わってしまわないように、なぜその動機を得るに至ったかの背景を作者自身がしっかり把握しておく必要があります。
実際の背景の考え方
さきほどの「動機がないキャラクターが主人公だとどうなる?」の例を使って考えてみましょう。
- ヒロイン:「冒険に出ようよ!」
- 主人公:「え、別にいいや。俺は部屋にいるよ」
- 幼いころ冒険に出て痛い目にあった
- 『二度とあんな目には遭いたくない』
- 父が冒険者をしていたがある日帰らぬ人となった
- 『冒険の怖さと肉親を失う悲しみがまだ残っている』
- 部屋から出ると死ぬ呪いが掛かっている
- 『死にたくない』

③がヤバすぎないか。
透明.png)
でもこれ、「本当は冒険に出たいけど……」って本心が加わると結構良い推進力を発揮するよ。その呪いを解くためにがんばろうとするはずだし。
キャラクターには心があります。
動機が強ければ強いほど、必ず理由があるはずです。
その理由をどんどん掘り下げていくと、状況に応じた主人公の選択に書く側も自信が持てるようになります。
必ずしもその理由を作中で説明する必要はありませんが、書かないにしてもちゃんと作っておくことがなによりも重要なのです。
透明.png)
ドSになれ! 心を鬼にしろ! お前は主人公の敵だッ!!

(ご愁傷様である……)
魅力的なキャラクターを実例を挙げて考えてみる
さて、キャラクターの動機とその背景の重要性についてここまでにご説明しました。
しかし、説明だけだとしっくりこないかもしれないので、実例を挙げて考えてみます。
誰もが知っているような超人気作は、たいていこの動機づけがしっかりしています。
ONE PIECE
誰もが知っているであろうこの作品。
「良い冒頭とはなにか?」 を考えるためにも結構読みました。
ワンピースってキャラクターがとにかく魅力的なんですよ。
今回は物語の核となっている主人公ルフィの動機と、その動機の背景について考えてみます。
海賊王になりたい。
シャンクスという海賊との交流。そしてシャンクスに命を救われ、その強さと心意気に憧れた。
憧れの海賊の中でも一番といわれるのが、ワンピースという秘宝を見つけた海賊=海賊王だから。
ワンピースの主人公ルフィの動機と背景はこのようになっています。
実はこの一話の中にはこれ以外にもキャラクターの魅力を増す要素がちりばめられていて、シンプルに見えて実はすさまじい第1話だったりします。
ナルト
ジャンプ続きでなんですが、ナルトもまた知らない人はいないであろう超人気作ですよね。
ナルトもまたキャラクターに関して超王道というか、非の打ちどころのない描写と設定をしています。
主人公のナルトに関して見てみるとこうなります。
火影になりたい(みんなに認められたい)。
忍の里で落ちこぼれ(&バケモノ)と虐げられていて、そんな自分がみんなに認められるためには忍の頂点である火影になるしかないと思った。
独自の「忍者」という文化がある前提の設定ではありますが、 ワンピースよりこちらのほうが少しわかりやすいのではないかと思います。
人には承認欲求があるので、よりダイレイクトに読む人の共感を誘う構造ではないでしょうか。
まあそのあたりの小難しい分析は置いておいて、ナルトはもう超王道な主人公設定になってます。
それでいて「忍者」という独特の世界観を持つので、王道でありながら斬新という実にバランスの取れたキャラクター設定でもあります。
ナルトももちろんこれだけではなくて、化物と揶揄される理由があとから独自の強み=特別性につながったりと、これまたいろいろ良いものを詰め込んでいるのですが、基本となる動機と背景がとにかくしっかりしているのが特徴です。
鋼の錬金術師
この作品はほんっっっとうによく練られた作品です。
設定力やら構成力で言ったら最強なんじゃないかとすら思います。
この鋼の錬金術師も超人気作ですが、当然のごとく一話における主人公の動機とその背景の魅せ方がすばらしいです。
錬金術で母を錬成するため、それを可能にする賢者の石が欲しい。
早くに死んでしまった母にもう一度会いたいから。
シンプル・イズ・ザ・ベスト。
そして強烈。
錬金術という特殊な技術がある世界観、一度母を錬成しようとして失敗した過去、それでも見つけた可能性を追って旅をする主人公。
この、シンプルで、強烈で、わかりやすい、と三拍子がそろった動機の魅せ方もまたすばらしいです。
そしてちゃんとこの動機がすべての軸になって物語が進んでいくので、ストーリー自体もブレがなくわかりやすい。
最終的には敵キャラの陰謀やら思惑やらがからまって複雑なストーリーになりますが、それでも混乱することなく読ませてくれるところにこの作品のすごさがあります。
鋼の錬金術師の1巻についてさらにくわしく分析しました!
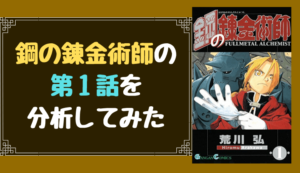
まとめ:魅力的なキャラクターは動機とその背景があってこそ
いくつか超人気作を挙げてキャラクターの持つ動機とその背景の重要性について説明しました。
おもしろい作品(人気な作品)というのはこの二つが本当にしっかり練られています。
繰り返しますが、魅力的なキャラクターを作りたいという人は、次の2つのステップを基本にキャラクター作りをしてみてください。
そのキャラクターの欲求を洗い出し、キャラクター性の軸となる動機を明確にする。
どうしてそのキャラクターがその動機(欲求)を得るに至ったかを考える。過去の出来事などと絡めておくとより土台がしっかりする。
もし「この作品大丈夫かな?」「ちゃんとおもしろいかな?」と不安になったら、キャラクターの動機とその背景について少し振り返ってみてください。

【質問回答】キャラクターの個性がこもったセリフが思い浮かばない時は
メールフォームからこんな質問を頂きました。
キャラクターの個性がしっかり反映されている台詞がなかなか出てこないのですが、どうすればいいでしょうか。
本記事の補足としてこの質問に答えてみようと思います。
メールフォームはこちら(なんでも質問してね)
キャラクターの個性が示されたセリフがうまく書けない
セリフって確かに難しいですよね。
魅力的なセリフについては、言い回しなどの妙もあるとは思いますが、表現力という意味では文章の上達と同じです。
- そのキャラクターが口にして違和感のない言葉(あるいは言いそうなこと)を
- 適切な使い方で口にする
ことが重要だと思います。
そのためには「そのキャラクターがどんなキャラクターなのか」をしっかりと作者自身が理解しておくことが重要です。
- キャラクターの生まれ育った背景
- 契機となった体験など
そのうえで、さらにわかりやすくセリフに個性を持たせたいのであれば、口調そのものにキャラクター性を付与してしまうのも効果的です。
一番簡単なものだと、語尾ですね。
語尾に特徴を持たせる
- ~です
- ~だ
- ~である
- ~なのじゃ
- ~ござる
安易といえば安易でしょう。
しかし安易だからこそのわかりやすさがあります。
一人称を工夫する
これも語尾と同じようなものですが、一人称の違いについて、読者はそこまで敏感ではないと思います。
さすがに今まで「俺」と言っていたキャラが急に「僕」になったらおかしいとは思いますが、漢字にするか、ひらくか、くらいではあまり効果はないかなぁ、というのが正直なところ。でも私はやっています。
- 俺
- オレ
- おれ
- 僕
- ボク
- 私
- わたし
- ワタシ
- わたくし
同じ音の一人称でも、文字として書くと印象が変わります。
特にカタカナ系はかなり特徴が出るので、うまく使うとキャラ付けに有効でしょう。
ちなみにわたしは不気味な敵キャラを描くときによく「ボク」とか「ワタシ」を使います。
「ワタシ」は使いようによってはチープ感も出てしまうのですが、しっかりと不気味さを演出しておけば結構有効なんじゃないかなと勝手に思ってます。
こんな例もあるよ(笑い声での特徴づけ)
ワンピースって、各キャラの笑い声がかなり特徴的ですよね。
ワンピースは漫画なのでそもそもが絵で書き分けがされますが、小説でもこういうテクニックは有効だと思います。
特にワンピースのような登場人物の多い作品の場合は、いかに読者にそのキャラクターを正しく認知してもらうかが重要なので、ぬかりないな、という印象。

キャラクターたちに鍋を囲ませる(つつかせる)
よく各キャラクターの完成度や特徴について考えるときに、
キャラクターたちに鍋を囲ませろ(つつかせろ)
というものがあります。
要するに、こたつの上にぐつぐつ煮える具材が入った鍋を置いて、その周りに各キャラクターを配置し、彼らがどういう行動や言動をとるのかシミュレーションをするわけです。
たとえば、百魔の主を例にするとこうなります。
- メレア:自分の好きなものをひょいひょいとっていく
- エルマ:肉を食べ続ける
- アイズ:周りのみんなが好きなものを食べられるように気にしつつ残りそうな具材を取る
- サルマーン:メレアやエルマに「肉ばっかとるんじゃねえ!」と突っ込みながら双子に野菜を取る(で自分が食べるのを忘れる)
- マリーザ:メレアのほうにメレアの好物を寄せておく
- リリウム:「自由すぎるわ……」と言いながら静かにバランスよく食べる
- シャウ:鍋の予算を考えたり余った具材をどこに卸すか考えてる
このキャラクターならこう動く、というのができてくれば、自然とそのキャラが言いそうなセリフは出てきます。
逆に、ここでキャラクターが自然と動かない&動きや言動に理由がないなどの場合は、一度キャラクターそのものを練り直してみるべきでしょう。
そもそもキャラクターがうまく作れない時は
で、そもそもの話、「うまく個性的なキャラクターが作れない」という場合はまずその練習からです。
具体的には文章の練習をするときと同じで、自分の知っている別作品の好きなキャラクターを真似して動かしてみてください。
- あなたの知っている好きなキャラクター
- 良いと思ったキャラクター
- これは個性的だなぁと思ったキャラクター
小説でも、漫画でも、アニメのキャラでも構いません。
彼らを頭の中に思い浮かべて、彼らが鍋をつついたときにどういう言動をとるかを考えてみてください。
二次創作はキャラクターを描写する力をつける上では有効
そういう意味では、二次創作というのもキャラクターを描写する力をつける上では有効なのではないかな、と思います。
透明.png)
それを徐々に一次創作に活かしていくイメージ。
必ずしもすべてにおいて新しいキャラクターでなくてもいいと思うよ。
結論:文字の上でわかりやすい差異をつけるorそもそも個性を出せるキャラ造形を(真似して訓練もあり)
キャラクターの個性ってなに?といわれると難しいものがあります。
でも、読む人にとって、
- 「こいつならこういう言動たしかにしそうだな」
- 「こいつならこの場面でこう動くだろうな」
という共通認識が生まれていれば、それはキャラクターの個性といってさしつかえありません。
なにも特徴的な決め台詞が必要なわけではなくて、一人の感情のある人間を描くつもりで、キャラクターのことを考えてあげるとよいでしょう。
透明.png)
ちなみにキャラクターを制するものは物語を制する。
魅力的なキャラクターって、本当に強いです。
かくいう私も常日頃から悩んでいる事柄ですので、これからもなにか「こういうのいいよね」ってのが思いつけばブログに書いていこうと思います。
透明.png)
質問をしてくれた人、ありがとう!

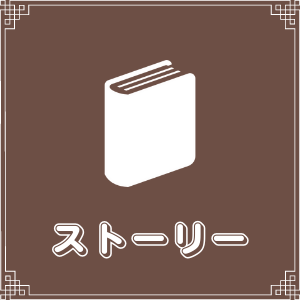



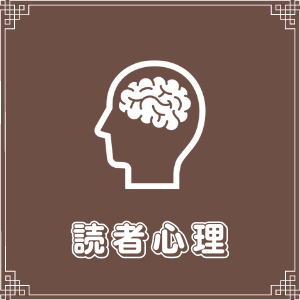



-300x300.png)




