小説の段落分けのルールや基準・使い方を作家が解説【文章作法】
前提:よくわかってなくても小説家にはなれる。
透明.png)
やあ、葵です。(@Aoi_Yamato_100)
みなさんは小説を書く時に段落分けについて悩んだことがありますか?
かくいう私は実際に小説を角川系列のレーベルから出版した経験があるのですが(既刊6冊)、そんな私も段落分けについて明確な基準を持っていません。
つまり、段落分けについてそんなに細かくこだわらなくても小説は出版できることを証明したわけですが、かといって「段落分けは適当でいいぞ!」というのもまったく答えになっていないし、「じゃあ段落分けしないで書く!」という極論を許容しているわけでもないので、「明確な基準とかルールとかは知らないけど私はこうしているよ」というのをご紹介したいと思います。
透明.png)
マジでいまだにルールとか基準とかわからない。

文章作法ってよくわからんもんが多いよな。
透明.png)
文章作法を気にして筆が進まないくらいならそんなものは捨ておけ‼
段落分けにおける基準やルールについて(一般事例)
日本語の文章における段落分けについては、小学校3年生あたりの国語で習います。
みなさんも文章のはじまりの1マス空いている部分に数字を書き込んだ覚えがあるはずです。私は忘れていました。
国語の授業においては、形式段落と意味段落という二つの段落について学んだはずです。
覚えていますか?
形式段落とは
形式段落(けいしきだんらく)とは、とりあえず1マス下げて書き始める「形の上での段落」を指します。文章の内容や区切り、文章の意味の変化などとは直接の関係がありません。
透明.png)
とりあえず1マス下げとこ。
意味段落とは
意味段落(いみだんらく)とは、「文章の内容やその変化に応じて分けた場合の文章のまとまり」を意味しています。意味段落は複数の形式段落で構成されているのが特徴です。
すごく簡単にいうと、もともと10個の形式段落で構成されている文章があったとして、そのうち①~③の段落が最初の意味段落、次の④~⑦が2つ目の意味段落、最後の⑧~⑩が最後の意味段落、というように、起承転結や序破急などに合わせて大きなまとまりとして見るのが意味段落です。
小説を書く上で意識すべきはどっち?
言葉の意味の上では、形式段落はあくまで文章の内容や意味とは直接関係がないと言います。
一方で、意味段落はそんな形式段落の集合体であると言います。
じゃあ結局形式段落ってどこで分けりゃええねん。
私も改めて形式段落と意味段落の意味を調べて、余計にわからなくなりました。
そんなわけで、二つの段落の違いについてはよくわからないのでいったん置いておいて、少し別の観点から段落の分け方について考えてみましょう。
小説を書く時に意識すべき段落分け
さて、本題に入ります。
小説を書く時にどのように段落分けをするべきか。
「絶対にこうしなきゃだめ!」というような明確なルールはありません。
しかし、段落(改行)がまったくない文章は非常に読みづらいものです。
透明.png)
誰しもが一度は経験があると思う。改行のない詰まった文章に関して読みづらいと思ったことが。私はもともと本嫌いだったので、それはもう何度も段落(改行)のない文章に挫折してきました。そのうえ句読点までないとなるとそりゃあもう読みづらいの極地で、目が滑ってスポーンと床に落ちてしまいそうな勢いでしたよところでこの文章についてはどう思いますか私はすごく読みづらいです。

……ッ!
このように、段落分けがされていない一連の文章は非常に読みづらくなります。
ですので、小説の文章の段落分けを考えるときは、まず「読みづらくなっていないか」を意識しましょう。
基本的に、一連の動作や状況を二つ以上の文章で説明する時には、段落を変える必要はありません。それは描写の対象が固定されており、続いていても違和感が出にくいからです。
ただし、一連の動作や状況の説明が四つも五つも連なる場合は、そもそもこんなに描写を重ねる必要があるかという観点で推敲した方が良いと思います。
一方で、Aのことを説明していたあとに、Bのことについて説明するときには、段落を変えた方が無難でしょう。
同じ繋がりだと思っていた文章が急にBのついての描写に切り替わると、読者が混乱してしまいます。
場面転換のとき
場面転換の際には基本的に段落を変えるべきです。
場面が変わるということは、描写する対象が必ず変わるはずだからです。
極端な例を出すと、Aさんが走っている様子を描写したあと、Aさんの3年後の生活の様子を描写するときなんかは、段落を変えないと読む方は時を飛ばされたかのような錯覚に陥ります。キングクリムゾン!
描写が切り替わるとき
たとえば、Aについての描写を書いていて、次にBについての描写を書きたい、という場面を想像してみてください。
想像だけだとなんなので例をあげてみます。
×悪い例
Aはとりあえず椅子に座ってお茶を一口すすった。それからほっと一息をつくと、鈍っていた思考が徐々に冴えていくのを感じた。やはり緊急時こそ一度落ち着くべきだな、とさきほどまでの慌てふためいていた自分を戒めつつ、今は遠く離れてしまっているBのことを思う。彼は無事だろうか。そのころBはちょうど富士山の山頂にいた。絶景だ。八合目であきらめずに最後まで登ってきてよかったと心の底から思った。
この文章は描写の切り替わりに際して段落変えをしなかった場合の文章です。
Aの描写をしていたと思ったら急にBの描写がはじまります。おそらく読んでいる人は「んん⁉」となったはずです。
上記の文章を正しく段落分けすると以下のようになります。
○良い例
Aはとりあえず椅子に座ってお茶を一口すすった。それからほっと一息をつくと、鈍っていた思考が徐々に冴えていくのを感じた。やはり緊急時こそ一度落ち着くべきだな、とさきほどまでの慌てふためいていた自分を戒めつつ、今は遠く離れてしまっているBのことを思う。彼は無事だろうか。
そのころBはちょうど富士山の山頂にいた。絶景だ。八合目であきらめずに最後まで登ってきてよかったと心の底から思った。
このように段落分けをすることで、読者に「ここで描写対象が切り替わりますよー!」というのを視覚的に伝えることができます。実はこれがとても大事です。
日本語の文章というのは、接続詞や倒置法、修飾語の有無などによって、主語が文章の中盤に出てくることがあります。(←これもそう)
主語が文章の中盤以降に出てくると、そこまで読まなければどんな意味の文章であるかが把握できません。
すると、主語にたどり着いて、描写対象が変わっていることを知ったときに「うおっ!この文章はAについてじゃなかったのか!」と読者は驚いてしまいます。情報の整理のためにも直近で読んだ文章を再度読み直さなければならないし、非常に面倒です。
物語に没入してもらいたいのであれば、同じ文章を二度読まなければならない状況がマイナスであることは忘れてはなりません。そのたった一つの違和感だけで、読者は物語体験からはじき出されてしまうのです。
透明.png)
まあ私は最近まであんまりよくわかってなかったんだけど。

お前よくそれで本出せたな!
一人称視点と三人称視点で描写の切り替わりは少し変わってくる
小説における描写というのは、一人称視点で小説を書いているときと、三人称視点で小説を書いているときでまったく変わってきます。
一人称視点での文章は、前提として主語に「僕」や「私」が入ってくるため、基本的に視点を所持している人間から見た描写が多くなります。というかほぼすべてそうです。
一方で、三人称視点は必要に応じて文章の前後で視点の保持者が変わります。Aさんの背後から見たBさんの状況だったり、Bさんの背後から見たAさんの描写だったり、という感じです。
また、そのうえで描写する対象がAになったりBになったりするため、一人称視点より文章の区切りが多く発生します。
結論:読者の視点を意識して、描写や場面が切り替わる時には段落分けしよう
結論を述べると、段落分けは読者の「読みやすさ」を意識して行いましょう。
もし、自分がなにかの文章を読んでいて、「この文章なんか読みづらいな」と思ったら、自分ならどこで文章を区切るかを考えてみると良いと思います。
小説の文章力を最速で上げる方法【おすすめの書き方と習慣】という記事でも書きましたが、段落分けも作家によってクセが異なります。
ですので、逆に「この人の文章はなんかスラスラ読めるな」という作家がいれば、ぜひ真似してみてください。
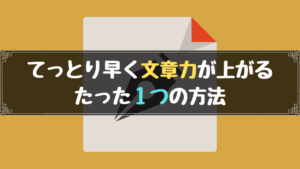

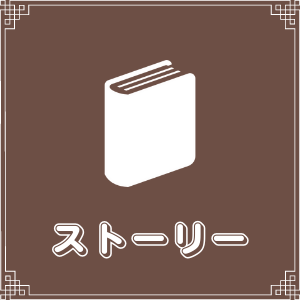



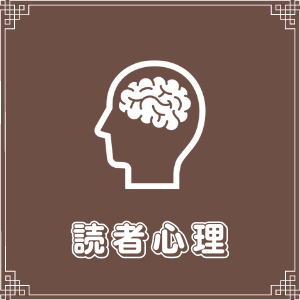



-300x300.png)

