哲学書って実は古代の魔導書なんだよって話【ファンタジーに例えよう】
透明.png)
やあ、葵です。(@Aoi_Yamato_100)
みなさん、哲学してますか?
こんな質問されたら大半の人間が目を丸くすると思います。

じゃあなんでそんな質問したんですか。
さて、哲学書と聞いてどんなイメージを持つでしょうか。
- なんかむずかしそう。
- そもそも哲学ってなによ。
- かんじよめない。
三番目はともかくとして哲学書ってなんだか読みづらそうって思いますよね。
かくいうわたしもそうでした。
わたしのようなあまり本を読んでこなかった人間にとって、哲学書はこう、読書家の中でも「レベルMAXで限凸済な人が読む本」という区分に無条件で入っていて、手にとったことなど当然なかったわけです。
透明.png)
あのコーナーは魔境だ……あっ、魔境の住人が立ち読みしてる……
でも、今となっては、わたしもそんな魔境の住人になりました。
きっかけは哲学書に対するある捉え方の変化にありました。
その哲学書、2000年前の人間が書いてるんだよ
その哲学書に対する捉え方の変化というのがこれです。
「神の子キリストが生まれるより前の人間が書いた本ってなんか古代の魔導書っぽくてかっこよくない?」
アオーイ・ヤマート(当時24歳の発言)
個人的に哲学書は「哲学したいから読む」というより、「イエス・キリストが生まれる前に生きていた人間が書いた古代の書物が読める」というところにモチベーションをおいたほうが燃えます。
ファンタジーが好きなそこにあなたならわかるはずです。
透明.png)
分かれ。

(唐突に横暴だ……)
想像してみてください。
今より2000年前の古代。神の子が生まれるよりさらに前に偉人たちが残した魔導書があった。
人々はその叡智にあずかるため、さまざまな手段を用いて魔導書を求めた―

(魔導書……?)
ときに争い、ときに手を取り合い、やがて魔導書の力によって混迷の世界に秩序が訪れる――
しかし人は愚かであり、いっときの平和も新たな魔導書の出現によって――

長いです。
いや、でも本当に、2000年以上も前の人間が書いた本が読めるってすごいロマンのあることだと思うんですよ。
せっかくなのでこれおもしろかったよってものを紹介したいと思います。
最初はとっつきづらいかもしれないですが、読んでみるとハマるかもしれませんよ。
とっつきやすい哲学書2選
生の短さについて 他2篇 (岩波文庫)
【概要】
生は浪費すれば短いが、活用すれば十分に長いと説く『生の短さについて』。心の平静を得るためにはどうすればよいかを説く『心の平静について』。快楽ではなく徳こそが善であり、幸福のための必要十分条件だと説く『幸福な生について』。実践を重んじるセネカ(前4頃―後65)の倫理学の特徴が最もよく出ている代表作3篇を収録。(新訳)
著者は小セネカ。出ましたよ紀元前。
キリスト降誕と同時期に生まれた人。
ついでにあの有名な第五代ローマ皇帝ネロの幼少期の家庭教師もしていた人。

「余だよ!」
(出典:Fate/Grand Order)

そうだけど違います。
透明.png)
かわいい……。
話がそれましたが、この「生の短さについて」はわたしがはじめて手にとった魔導書です。
通っていた本屋にフェアかなにかで平積みされていて、なにげなく著者説明欄を読んだとき、
「紀元前っ!? 古代人の魔導書やんけ!」
と「そんなことも知らなかったのか」と言われそうな感想を抱いてちょろっと中を読んでみました。
当時は結構将来に悩んでいて、「誰か頭の良い人になんかアドバイスもらえないかな」とか思っていたのですが、見事に小セネカ先生に諭されました。
こうすれば金持ちになれるとか、こうすればえらくなれるとか、そういう技術論や方法論があるわけではないのです。
でも、
- 「人間ってこういうものだよね」
- 「人生ってこういうものだよね」
そう淡々と語る小セネカ先生の言葉は、「わかるわかる」「2000年前の人間も同じこと考えてたのかぁ」となぜだかすんなり腹に落ちて、とても安心したのを覚えています。
有名どころの哲学書の中でも、かなり読みやすいほうだと思います。
内容も難しすぎず、さすがはあの暴君ネロの家庭教師というような、はじめての人にもわかりやすい切り口なので、気になる人はぜひ読んでみてください。
方法序説 (岩波文庫)
【概要】
すべての人が真理を見いだすための方法を求めて,思索を重ねたデカルト(1596-1650).「われ思う,ゆえにわれあり」は,その彼がいっさいの外的権威を否定して達した,思想の独立宣言である.本書で示される新しい哲学の根本原理と方法,自然の探求の展望などは,近代の礎を築くものとしてわたしたちの学問の基本的な枠組みをなしている.[新訳]
これは比較的新しい時代の魔導師が生んだ魔導書です。
「コギト・エルゴ・スム(我思う、故に我あり)」の一説はとても有名で、おそらく聞いたことがない人はいないでしょう。
ぶっちゃけわたしはこの魔導書を書いたデカルト先生はそこまで好きではないのですが(情念論とかなに言ってっかわかんなかった)、方法序説に書いてある「我思う、故に我あり」という思想を生んだ過程は「なるほどなぁ」と思いました。
この魔導書も読めばなにかすごい力が得られる、というわけではないのですが、読むとなんかスッキリするのでおすすめ。
そしてなにより短い。
透明.png)
初心者にとって短いというのはとっつきやすさの一つだよね。
長いと読み切れないし、頭痛くなるし。
逆にいえばこの短い書物の中に「我思う、故に我あり」の原理説明をぶち込んでしまったという点でおそろしい魔導書ではあるのですが、ともかく入門にはぴったりなのでおすすめです。
「そのセリフ、聞いたことはあるけど結局どういう意味なの?」と気になる方はぜひ一度読んでみてください。
まとめ:哲学書も案外悪くない
哲学書ってもちろんそこに書いてある思想を読んで「へぇー」とか「そうだなぁー」とか、あるいは「今も昔も考えてることは同じだな」とか納得したりして楽しめたりもしますが、
- 感情ってなに?
- 人間ってどんな生き物?
- 良い生き方ってなんだろう?
みたいに、その当時なんの定義もなかった空白にあたらしい価値と定義を見出していくという点でとても合理的なので、論理的な思考法を身につけるのにも実はとても役に立ちます。
もしそういった思考法を勉強したいという人にもぴったりなので、興味が出た方はこれを機に手に取ってみてはいかがでしょうか。
余談:著名な魔導師(哲学者)の一覧が知りたいという人は
透明.png)
この魔導師の手引きがとてもよくまとめられていて便利。

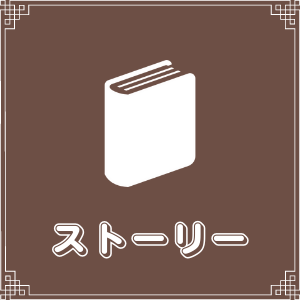



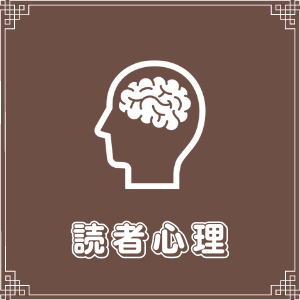



-300x300.png)




