ピンチの先に絶望が待っていてはいけない【物語展開への期待感】
透明.png)
やあ、葵です。(@Aoi_Yamato_100)
ピンチってどんな物語でも存在しますよね。
そしてピンチというのは物語に緩急をつけてくれるので、良質なストーリーにはなくてはならないものです。
しかし、ピンチが大きすぎると、「鬱展開」と呼ばれて一部の鬱展開スキーを除く多くの読者を振り落としてしまうことがあります。
これは、エンターテインメント小説として多くの読者を得たいときには、ハッキリと言って悪手です。
繰り返します。
鬱展開は悪手です。
透明.png)
賛否両論あるかもしれないけど、100万文字近くの長編を書いてきたわたしの実体験です。
読者がストレス展開に耐えられなくなってきている?
最近は、
- 読者の質が変わった
- ストレスフルな時代
- さらにストレスを与えられる展開は好まれない
と、読者側の質を問題にあげる人もいます。
わたしもそれがまったく影響していないとは思いませんし、少し前まではそれがすべてだと思っていました。
でも、最近またいろいろ考えてみると、ピンチはピンチでもその先に救いの兆しが見えるピンチはけっして悪い展開ではないように思えてきたのです。
ピンチの先に希望が見えるなら問題ない
ピンチの先に絶望が見えるシーンは、読む側にストレスを強います。
そして人間はできるだけストレスを避けようとする生き物なので、自分にとってストレスとなるような展開を先に察知すると、読むのをやめてしまいます。
透明.png)
テレビとかでハプニング映像が見れない人はわかると思う(わたしは見れない)
しかしながら、ピンチはピンチでも、
- 今はピンチだけこのキャラクターなら絶対に逆転してくれる
- きっとどこかで好転するに違いない
そういう希望が見えている場合、案外ピンチシーンも普通に読めてしまうのです。
先の展開に期待を持たせる
こういう希望を読者に見せるためには、ピンチになるメインキャラクターにおいて、
「でもこいつなら――!」
という期待をわかりやすく持たせてあげることです。
繰り返します。
ちゃんと、わかるようにです。(わかりづらい伏線とか本格ミステリー以外いらない)
その期待を裏切らないこと
「予想は裏切れ、期待は裏切るな」
誰が言ったのかは定かではありませんが、そんな言葉がストーリー作成のバイブルとして存在します。
これはまさしく金言と呼ぶべきもので、読者に抱かせた希望の期待を裏切るべきではありません。
どうやって期待を持たせるのか
では、実際にどうやって読者に希望を見せるのか。
パっと思いつくものだと次のようなものがあります。
- 隠された力がある
- 仲間が援軍に来る素振りを前の話で入れておく
- ピンチになるのが「でもこいつならやってくれる」と思えるキャラクターである
ピンチになるキャラクターが、助かる方法に関して目途がたてば十分です。
隠された力がある
これは昔からずっと存在するものです。
主人公に隠された力があるパターン。
主人公がそれを使おうと思っても意識的に使うことができないけれど、ピンチになったときは発揮されるだろうと読者が思える力のことです。
有名作品で言っても、
などなど、枚挙にいとまがありません。
実際、これらの主人公がピンチになって、その隠された力が発揮されて逆転するシーンというのは燃えるものです。
ゆえに、主人公が実はすぐれた血統の子どもだったり、実は特別な存在である、という設定は、「使い古されている」とどんなに揶揄されても、いつの時代でも王道として存在し続けているのです。
仲間が援軍に来る素振りを前の話で入れておく
これは戦記などでよく使える方法です。
ストーリー上で伏線を作る必要があるため、やや使うのには手間がかかりますが、実を結んだときには読者に高揚感を覚えさせることができます。
前の話で仲良くなったり、同盟を結んだり、そうした相手が、
「待たせたな」
と出てくるシーンはやっぱり燃えますよね。
パっと思いつくものだと中国の春秋戦国時代を描いた漫画『キングダム』の山の民の援軍シーンなんかはこれにあたります。
戦記系の話は多くの登場人物が戦場に置いて流動的に動くので、良くも悪くもなんでもおこりえます。
だからこそ、こういった「待たせたな」というシーンがとても書きやすい題材です。
「こいつならやってくれる」と思えるキャラクター
状況的にはあきらかにピンチだけれど、
「でもこいつならやってくれる……!」
そう思えるキャラクターっていますよね。
一番それが強い国民的人気キャラクターといえばドラゴンボールの孫悟空だと思います。

(出典:©バードスタジオ/集英社・フジテレビ・東映アニメーション『ドラゴンボール超』)
悟空は、
- 実はサイヤ人
- 地球育ちだからこそスーパーサイヤ人に目覚める可能性を持つ
などなど、隠された力=特別性という意味でも王道な要素を持ち合わせていますが、なんといってもその性格やこれまでの生き方が、「悟空ならやってくれる」と見る人に期待を持たせます。

(出典:ドラゴンボール)
透明.png)
クリリンのこのセリフがその性質のすべてを表している。
このように、作中キャラですら「こいつならやってくれる」と思うようなキャラクターは、ピンチに陥っても一定の逆転への期待感を持たせてくれます。
こういったキャラクターのピンチは、むしろ「逆転シーンへの期待感」から読者のページをめくる手を進ませる強い力になるのです。
まとめ:ピンチでも逆転への期待感を持たせるのが重要
こんな感じで、ピンチを描くなら一方的な鬱展開ではなく、
その先の展開への期待感を持たせる
のがとても重要です。
もしストーリーのうえで主人公たちのピンチを書く必要が出たときは、そのシーンがちゃんと逆転への期待感を含んでいるかを見直してみてください。
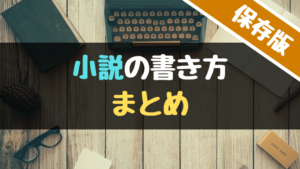

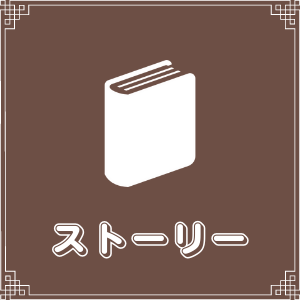



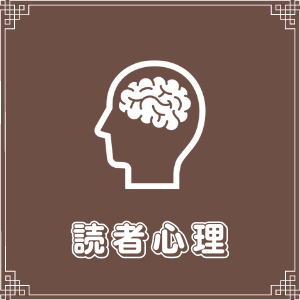



-300x300.png)


