物語におけるリアリティとは?意味とポイントを3つの視点から解説
透明.png)
やあ、葵です。(@Aoi_Yamato_100)
物語においてはリアリティが大事ってよく言われるけど、実際にリアリティってなんなの?
小説やマンガを書いている人は、一度はリアリティという言葉にぶつかったことがあると思います。
意味としては「現実感」。
透明.png)
じゃあその現実感ってどうやって出すのよ?
そんな疑問に答えるべく、本記事ではリアリティの意味について説明するとともに、リアリティを出すための方法についてもお話します。
リアリティとは『事物や人物の描写が自然に感じられるかどうか』
あらためてリアリティとはなにかについて考えてみます。
いろいろ調べたなかで、これが一番的を射ていると思ったリアリティについての説明がありました。
【リアリティ】:
realityを日本語にすると「現実」「現実性」などとなるが、また「迫真性」、あるいは「説得力」とも言い換えられる。現実の物理原則に沿っているか、というだけではなく、作品世界での理論が一貫しているか、事物・人物描写が自然に感じられるか、などということも含めるためである。ライトセーバーで切り合おうが美男美女しか出てこなかろうが、スター・ウォーズとガンダムにもリアリティは存在できるのだ。(出典:ニコニコ大百科)
まさしくこれが物語におけるリアリティといえます。
一番重要な点は、
事物や人物の描写が自然に感じられるかどうか
です。
物語において重要な3つのリアリティ
さて、リアリティの意味については概要がつかめました。
では、実際に物語を書くうえで重要なリアリティにはどういうものがあるかを考えてみましょう。
物語におけるリアリティには、次の3つがあります。
- キャラクターのリアリティ
- 世界観のリアリティ
- ストーリー展開のリアリティ
それぞれひとつずつ説明していきます。
キャラクターのリアリティ
キャラクターのリアリティというのは、
そのキャラクターの言動や行動が自然に感じられるか
にあります。
具体的な例をあげると、次のようなものはリアリティがないと言えるでしょう。
- 一般町民がなにくわぬ顔で城に出入りしている
- 甘いものが苦手なのにケーキを食べている
- 外出が嫌いなのに「外に行こう」とか言い出した
これらは、そのキャラクターが持っている性質(性格)と実際の描写がズレてしまっています。
逆に、
- 王様が城に出入りしている
- 甘いものが好きでいつもケーキを食べている
- 外出が嫌いなので「僕は家にいる」と言っている
こうするとなんら不自然なところはありません。
そのキャラクターはどういった人物なのか
キャラクターのリアリティは、基本的に出そうと思って出すものではありません。
勝手に出るものです。
そもそもキャラクターというのは、作られた時点で一定のリアリティを持ちます。
- 性別
- 身分
- 年齢
- 職業
こういったキャラクターの持つ性質そのものが、リアリティに繋がっています。
ですが、そういう性質に見合わない行動や言動を取ると、とたんにリアリティが失せます。
キャラクターのリアリティは引き算に気をつける
基本的に、キャラクターがどういった人物なのかがしっかりと決まっていれば、おのずとリアリティは出ます。
透明.png)
キャラクターの作り方については『魅力的なキャラクターの作り方!2つのステップを実例付きで解説』という記事で解説しているのでそっちを参考にしてね。
もちろん、『こいつはこういうキャラクターです』というのを読者に理解させるために、そのキャラクターの性質に基づいた描写を加えるのはありです。
身分や職業で特徴づけするのが難しい場合には、描写を付け加えてみましょう。
しかし、キャラクターのリアリティにおいて最も気をつけるべきは、リアリティが損なわれないようにすることです。
さきほどの例にもあげたとおり、
- 一般町民がなにくわぬ顔で城に出入りしている
- 甘いものが苦手なのにケーキを食べている
- 外出が嫌いなのに「外に行こう」とか言い出した
こういう自体が起こらないように常に意識してください。
- こいつはこういうことを言うか?
- 根底にある主義主張とズレていないか?
- なんとなく書いたけどキャラクターの性質と合っているか?
キャラクターのリアリティというのは引き算で、がんばって描写してもくどくなるわりに、その性質にそぐわない描写を入れると途端にリアリティがなくなります。
後述する世界観のリアリティやストーリー展開のリアリティと比べると、非常にデリケートです。
世界観のリアリティ
次に世界観のリアリティについて説明します。
これは、物語上の世界観、舞台設定の土台となるものです。
世界観と一口にいっても、
- ファンタジー
- SF
- 現代
- 過去の時代
いろいろあります。
中でも、もっとも自由なのがファンタジーですが、ファンタジーの世界観もあまりに無節操だと読者からリアリティを奪ってしまいます。
世界観のリアリティは人間を基準に考える
世界観のリアリティをたしかなものにするためにもっとも良い方法は、描写はしないけれども『どういう世界』であるかを設定しておくことです。
エピック・ファンタジーくらい作り込めとは言いませんが、どこにどういう国があって、どういう文化が発展して、その国ではどういう職業が多いのか、などについてはあらかじめ練っておくのが良いでしょう。
結論としては、気候や地形を考えたあとは、人間を基準に考えることです。
読者は人間である
その物語の読者は人間です。
ゆえに、
人間はその気候や土地において、どういう行動を取るだろう?
という疑問をもとに世界観を作ってみてください。
そんなに難しく考えなくて大丈夫です。
例をあげるとこんな感じです。
- 周りに川が多いので水運が発達した
- 水運が発達した影響で商業が盛んになった
- 商業が発達したのでその国は財力が強い
- 財力が強いので戦争も強いが、利権を独占しているので近隣諸国から妬まれている
- 近隣諸国が結託して戦争になった
こんな感じで、ひとつの地方で世界観のストーリーが出来上がります。
こういうものが積み重なると、重厚な、とても奥行きがある世界観が作れます。
ちなみに、ちまたで人気な『異世界転生もの』は、実のところ世界観のリアリティを損ないやすい要素を抱えています。
気になる人はこちらの記事へ
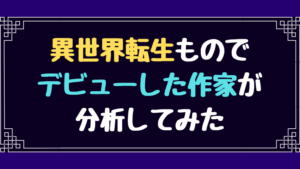
ストーリー展開のリアリティ
ストーリー展開のリアリティとは、これまで述べてきた2つのリアリティが合わさって生み出されるものです。
- キャラクターのリアリティ
- 世界観のリアリティ
ストーリーとは、キャラクターの行動によって展開が進みます。
そのストーリーにリアリティがあるかどうかは、キャラクターたちが、その世界観を飛び越えない範囲で、その性質に見合った行動を取ったかどうかで判断されます。
ストーリー展開のリアリティは集大成
極端な例をあげると、魔法の存在しない世界観で、戦士風のキャラクターがいきなり魔法を使って目の前の問題を解決したら、リアリティもなにもあったものではありませんよね?
作者がストーリー上の問題を、とにかく先に進めたいからと無理やりに解決してしまったようなものです。
もしこれをしてしまったら、ご都合主義と呼ばれてもなんの文句も言えません。
ご都合主義(ごつごうしゅぎ):
立場や主張に一貫性が無くその場その場で都合よく態度を変えることなどを意味する。単純に自分の都合のいいようにしか行動しない人も指す時もある。
(ニコニコ大百科)
ストーリー展開のリアリティは、キャラクターのリアリティと世界観のリアリティの2つの上に成り立っています。
魔法のない世界で、戦士風の男が、目の前の問題を解決するためにどうすればいいのか。
それを作者も考えなければならないのです。
まとめ:リアリティは『自然』かどうかを常に考える
リアリティというのは、積み上がるものです。
そして一つのリアリティは、ほかのリアリティに関連します。
- キャラクターのリアリティ
- 世界観のリアリティ
この2つが大きな意味での作中世界のリアリティを形成し、ストーリー展開のリアリティが作品全体としてのリアリティを規定するのです。
もし自分の作品に対して「リアリティちゃんとあるかなぁ」と不安に思ったら、一度この3つのリアリティがしっかり通っているか見直してみてください。
透明.png)
ちなみに一番大事なのはキャラクターのリアリティだよ。

ストーリーはキャラクターが進めるものだからな。

余談:『あるある』こそがリアリティの源泉なんじゃないのって話
こういうリアリティってささいなところに現れます。
さすがにうんこを駐車場でする人はあまりいませんが、逆にトイレでうんこをするのは当たり前すぎますよね。
だから、読者からしても意識にとまらないわけです。

うんこする描写が入ったら意識しまくるけどな! 珍しすぎて!
だから、生活上そこまで当たり前すぎるわけでもないけど、「こうなったらそうなるよね」「ああ、あるある」って思わず思ってしまうような事柄こそ、それが自然かどうかしっかりと見極める必要があります。
透明.png)
このニュアンスが難しい。
ひょんなことで意識する描写、かつ、「あるある」「そうそう」と思うシチュエーション。
こういう細部にこそ、リアリティが宿り、それが作品を支えます。
そして『あるある』に共感をすると、読者は知らずのうちに作品世界に一歩のめり込みます。
その積み重ねがやがて、作中世界への没入を促すのです。
透明.png)
無理して入れる必要はないけど、そのシチュエーション上で使えそうな『あるある』は入れていったほうが読者を引き込むフックができていいよね。

まあ、たしかにな。
透明.png)
その性質上、冒頭にこそこういう『あるあるフック』が必要なんじゃないかな、と思いました。

(ついに変な名前つけやがった)
- 人は駐車場でうんこはしない
- 『あるあるフック』が大事
- 冒頭でこそ威力を発揮するかも

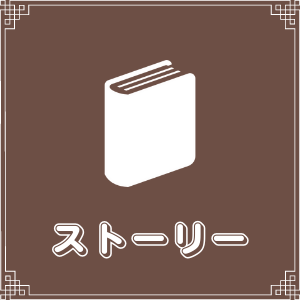



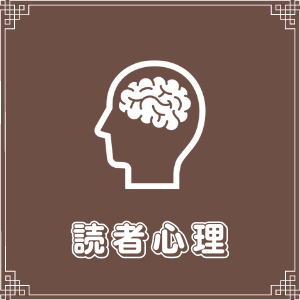



-300x300.png)

