文章の推敲方法を例文付きで解説!見るべき3つのポイント【コツ】
透明.png)
やあ、葵です。(@Aoi_Yamato_100)
小説は推敲(すいこう)が大事というけれど、どこを直すのがもっとも効果的なのかわからない。
そんな『推敲のやり方がいまいちわからない』という人のために、葵大和がおすすめする特に見るべき推敲ポイント3選をご紹介します。
10年以上小説を書いてきた経験談と、実際に小説を出版するに際して編集者から言われたポイントを踏まえているので、なかなか参考になると思います。
透明.png)
ここを見ておけば間違いなく文章は良くなる。超基本でもあるので、まずは今回紹介する3つのポイントを押さえてみよう。
小説の文章を読みやすくするためのオススメ推敲ポイント3選

最初に結論から言っておくと、主なポイントは以下の3つです。
- 同じ意味の文章が並んでいないか
- 読めない漢字はないか
- 誤字脱字はないか
それぞれ個別に説明していきます。
①:同じ意味の文章が並んでいないかを確認する
「同じ意味の文章が並んでいる」のは、かなり読みやすさに悪影響があります。
わたし自身これでかなりの失敗をしてきたので、ぜひ推敲時には確認してもらいたいポイントです。
実際に例をあげてみましょう。
太郎は椅子に座ってから怪訝な表情を浮かべた。
眉をひそめていぶかしげに花子を見る。
「花子、おまえ――」
\うんこ漏らしたのか?/
透明-740x740.png)

……。
透明.png)
すみませんなんでもないです。
さて、この例文ですが、とりあえずとってもアウトです。(うんこの部分じゃないよ)
この文章は、二行目を削除して、一行目だけで十分です。
- 「怪訝=いぶかしい」が同じ意味
- 「眉をひそめて」をわざわざ入れなくても「怪訝(けげん)な表情を浮かべた」で十分に状況を説明できている
同じ意味の文章が続くと、文章のリズムがとても悪くなります。
読者は頭の中で状況を想像しながら文章を読み進めます。
その関係で、同じ動作や状況の説明が二度続くと、作品への没入感が失われてしまいます。
もっとわかりやすくしてみましょう。
太郎は椅子に座った。
太郎は椅子に腰かけた。
「花子、おまえうんこもらしたのか?」
この「太郎は椅子に腰かけた」って文章、邪魔者以外の何者でもないでしょう?

邪魔なのはうんこもです。
これは誰もがやりがちなポイントで、かつ、かなり重大な文章の誤りです。
読者はこういう文章を見た瞬間、読むのをやめてしまうことさえあります。(実際にわたしもよく指摘されました)
こういう文章を発見したら、容赦なく削除してください。
文章に関して言えば、「なんの益(えき)もなく害しかもたらさない極悪な文章」というものが存在します。
「それでもあなたは生きていていいのよ……」とか慈悲を与える必要はないのです。
透明.png)
やつだッ! 消せ!!
②:読めない漢字をひらく
書いているほうは読めるが、一般的な読者は読めないという漢字があります。
なぜ書いているほうは読めるのか。
透明.png)
意味から入ってパソコンの変換先生に教えてもらってるからだよ!!
- 普段使わないような漢字は使わないほうがいい
- 自分で書けない漢字も使わないほうがいい
むしろ書ける漢字も「中学生くらいだと読めないかな……?」と思うのであればひらいたほうがいいことが多いです。
もちろん、難しい漢字でも「どうしてもここはこの漢字じゃないとダメだ!」というのであれば使ってもいいとは思います。
しかし、読者の「読みやすさ」を考えるのであれば、そもそも別のわかりやすい言葉を使ったほうがいいでしょう。
誰かに読んでほしいと思っているなら、読みやすさは正義です。
実際に書店で売られている小説を手に取って、どの漢字に「フリガナ」が振られているかを意識して読むと、読める読めないのラインがわかるのでおすすめです。
ちなみに「漢字のひらきかた」にも作家の個性がよく出るので、好きな作家の作品を読むときには少し注意して読んでみるとおもしろいです。
③:誤字脱字を直す
書けば書くほど増える誤字脱字。
書き続けるかぎりこいつが消えることはないんじゃないかと思っている。
そんな誤字脱字さんたちですが、些細なわりに読むほうにとっては一大事。
誤字脱字にもヤバさのレベルがあって、弱めのやつならまだいいんですが、物語世界を楽しんでいた読者を一発で現実に引き戻すレベルのやつもいます。
書くのに慣れていない段階だと誤字脱字というのは頻発するものなので、推敲時はよく確認してください。
誤字脱字に見つけ方や直し方については下記の記事でくわしく書いているので、参考に。
まとめ:小説を推敲するときはこの3つのポイントを見る
もう一度「特に注意してみるべき推敲ポイント」を確認しておきましょう。
- 同じ意味の文章が並んでいないかを確認する
- 読めない漢字をひらく
- 誤字脱字を直す
これを押さえるだけでも文章としてはかなり完成度が高くなるので、推敲の際にはぜひ参考にしてください。
余談:疲れている時にだけ出来る特殊な推敲方法もある
文章を読むのってめちゃくちゃエネルギーを使う作業です。
言葉を読んで、文脈を理解して、そして想像をする。その文章にむずかしい言葉や読みづらい部分があると、途端に理解が出来なくなります。ましてや、疲れているときなんかは何度読んでも文脈や意味が頭に入ってきません。
だからこそ、「疲れてるときに読める文章は「本当に読みやすい」文章なんじゃないか?」という説が浮かびあがります。
なぜこんなことを書いているのかと言うと、
透明-740x740.png)
/今まさに疲れているからである\

休めよ。
しかしこうも考えられませんか。疲れているときも活用できるなら無駄がない、と。うまく文脈を読みとることができない状態でもなお読める文章は、最高に読みやすい文章なのだと!
というわけで、そんな思考から編み出された奥義を伝授します。
その名も「疲れ推敲」(奥義)。

いやだから休めよ。
疲れているときにこそ文章を見直してみよう
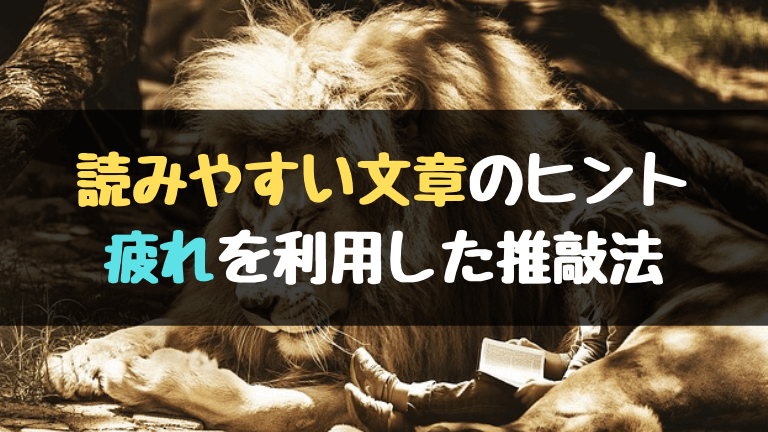
疲れ推敲は「疲れていて新しく文章を書き起こす気力がない」ときにこそ威力を発揮する作業です。しかし、これにはあとで必ずやらなければならない作業があります。
それが、実際の書き直し作業はちゃんと休んだあとにやるです。
理由は、冒頭でも述べたとおり、書く側も文脈を把握する力が落ちているからです。あと、疲れているときは誤字や脱字には気づきにくいというのも理由です。
透明.png)
読み飛ばしちゃうんだよね。ナチュラルに。
つまり書く側としては、次のような順序で推敲を行うと良いでしょう。
①:まずは疲れる
これは肉体的疲労も当然ながら、特に脳の疲れに気を遣うと良い。認知機能が下がった状態をなんとか作る。
透明-740x740.png)
/そうだ、残業しよう\

「京都行こう」みたいなノリで言うのやめてもらってもいいですか?
②:文章を読んで「なに言ってるかわからねえ」って部分にチェックを入れる
何度も言いますが修正はあとにしましょう。その状態で修正を行ってもミイラ取りがミイラになるだけです。あくまでチェックを入れるだけ。
もし「まったく文章が入ってこねえ!」って場合は大人しく寝てください。
③:しっかり回復したあとに書きなおす(重要)
文章を書く行為はかなり大きな力を使うので、疲れているときはうまく言葉が出てこなかったり、同じ意味の文章を繰り返してしまいがちです。
そして、認知機能が下がっている状態では細かい部分を読み飛ばしてしまうので、細かい作業には向きません。
透明.png)
文脈を拾う力も激減しているため、ストーリー展開などの手直しも厳禁!
まずはたっぷり寝る。そのあと起き抜けざまにチェックを入れた箇所を手直しする。
しっかりと寝たあとはかなり認知機能も回復しているので、読みにくかった部分を理性的に推敲することができるようになります。
疲れ推敲のポイント:あくまで『文章』を直すことに絞ること
つまりストーリーについては放っておくこと。
あくまで文章として読みやすいか否かについてピンポイントで推敲することが重要です。

ストーリーは話の筋を論理的に組み立てる必要があるからな。
ちなみにこの方法は「疲れているときもなんか創作のために使えないかな」という創作中毒者向けの方法ですので、無理は禁物です。
基本的に小説は、心身のコンディションが整っているときに推敲するのがベストです。
透明.png)
でも、いてもたってもいられないときってあるよね。
ふと「ああ、今疲れてるな」と思ったときにちょっと試してみるくらいの気持ちで、参考までに。
![]()

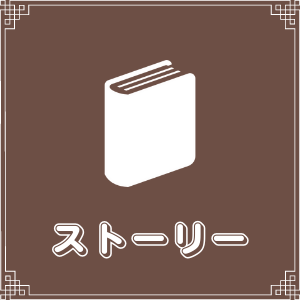



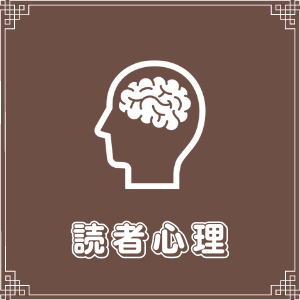



-300x300.png)


