『鋼の錬金術師』の第1話がいかに優れているかを分析してみた【ストーリー分析】
透明.png)
やあ、葵です。(@Aoi_Yamato_100)
『鋼の錬金術師』といえば名作漫画として名高いですね。
名作には名作たりえる理由があります。
わたしが『魅力的な冒頭』をいろいろ分析していたときに、鋼の錬金術師(漫画)の第一話についても分析していました。
で、ほかの漫画と比べても鋼の錬金術師は特に冒頭が優れていると思うので、備忘録がてら『鋼の錬金術師の第一話の優れている部分』をまとめてみます。
小説や漫画にかぎらず、すぐれたストーリー作りの参考になると思うので気になる方は読んでみてください。
『鋼の錬金術師』の第1話がいかに優れているか
鋼の錬金術師の第1話の簡単な流れは以下のとおりです。
- なにやら物騒なシーンからはじまる(『持って行かれた』のシーン)
- 主人公たちの描写(『錬金術師』という職業人であることが判明)
- 錬金術がどんなものかの説明
- 悪そうなやつが出てくる(司祭)
- エドワードの目的が匂わされる
- ピンチと小さなどんでん返しの連続
- 最後にカッコいい引きのシーン
それぞれ順番に見ていきましょう。
物騒なシーンからはじまる(『持って行かれた』のシーン)
以前に『読者を引き込む魅力的な冒頭とは』という記事でも書いたとおり、読者の気を引くために冒頭に衝撃的なシーンを持ってくることはとても有効です。
あらゆるエンタメ作品でその手法が使われているため、こういうはじまり方自体は真新しくはありませんが、有効だからこそ使い古されているわけであって、けっしてこういうはじまり方が悪いわけではありません。
むしろ、『鋼の錬金術師』はあらゆる王道をしっかりと盛り込み、そのうえで独自性も光る、非常に整った作品なので、こういうところは参考にするべきでしょう。
のちのち、この『持って行かれた』のシーンが主人公たち(エドワード・アルフォンス)の行動の動機として回収されるので、むしろなくてはならないシーンでもあります。
- 衝撃的なシーンで読者を一気に引きこんでいる
- のちに主人公たちの『動機』に繋がるシーンでもある(伏線)
主人公たちの描写(『錬金術師』という職業人であることが判明)
早い段階で『錬金術』を披露しているのも重要です。(具体的には錬金術でラジオを直しています)
『錬金術ってまだなんかよくわからないけど、魔法的な力で物を直せる』
くらいの認識が読者の中に生まれます。
そのうえで周りのキャラクターの驚きから、主人公であるエドワードたちがそこそこ名の知れた人物であることもうかがえます。
- 実はすごいのかも?
- これからこの主人公たちがなにかしてくれるのかな
ハッキリとではありませんが、そういう期待感が煽られますね。
また、早い段階でしっかりと登場人物たちの身分や職業をあきらかにするのは、キャラクターを覚えてもらうのに非常に重要です。
加えて、ここでエドワードのコンプレックス(チビと言われる)も明らかになっているのが、エドワードへの親近感を抱く助けになっています。
透明.png)
ただすごいだけのキャラクターより、身近なコンプレックスを持っているキャラクターのほうが好かれる傾向があるよ。
錬金術がどんなものかの説明
このシーンのあとで、錬金術がどんなものであるかの説明が入ります。
この部分は非常に文字が多いので賛否両論ですが、冒頭から主人公描写とするする入って、リズム的には悪くない位置だと思います。
ただ、最近のほかの漫画と比べるとやや説明っぽさが強いので、人によってはダメかもしれません。
とはいえ、第一話の構成上、ここで錬金術に『等価交換』の原則があることを説明しておかないと、このあとに出てくる『賢者の石』の話が出せないので必要な説明です。
悪そうなやつが出てくる(司祭)
はい、ここ重要です。
第一話の中で、ちゃんと悪そうなやつが出てきます。
基本的にストーリーは『対立構造』があると締まります。
主人公が出てきたら、その主人公と対立する勢力を出すと、より主人公たちが輝くわけです。
ほかの名作と呼ばれる作品にも、とりあえず第一話だけ出てくる『いかにも悪そうなやつ』がいます。
鋼の錬金術師に関しては、このあと主人公たちの動機やその背景と関連する『賢者の石』を、どうやらこの司祭が持っているらしい、ということで繋がりが生まれます。
鋼の錬金術師の第一話において、この司祭の存在が非常に重要です。
司祭が、賢者の石っぽいものを持っていることこそが、鋼の錬金術師という物語の第一話を良い意味で凝縮させています。

司祭に人気はないが……
透明.png)
ちゃんと悪役している点で、メタ的には良いキャラクターである。
エドワードの目的が匂わされる
このあたりで読者を飽きさせないために事態が急変します。
アルフォンスの首が吹っ飛ばされたり、司祭が悪役っぷりを露わにしたり。
で、その間にどうやらエドワードたちが『賢者の石』を探しているっぽいことが匂わされます。
まだ明確な動機ではありませんが、キャラクターに目的があることを匂わせるのは、物語にちゃんとした方向性を付加するので、非常に重要です。
このあたりは錬金術の説明とも絡む形で、徐々に輪郭が見えていく感じ。
ピンチと小さなどんでん返しの連続
司祭とエドワードたちが邂逅してからは、小さなどんでん返しを繰り返して一気に物語が進んでいきます。
起承転結でいう『転』の連続ですね。
ちなみに鋼の錬金術師の第一話は起承転結が非常にきれいに構成されています。
そのうえ、『転』を何度も繰り返すことで、読者を飽きさせません。
最後にカッコいい引きのシーン
そうやって『転』である小さなどんでん返しを連続したあとに、満を持して見せ場のシーンが入ります。
エドワードが『鋼の錬金術師』と呼ばれる理由もここで判明し、タイトルもしっかり回収していくという抜かりのないスタイル。
そしてここで『人体錬成を行った人間の末路』というワードが出てくるので、勘のいい人はエドワードの手足が義手であることと、冒頭の『持って行かれた』のシーンを結びつけます。
そこが結びつくと、
- やっぱり冒頭のシーンが関係しているっぽいな
- じゃあなんでエドワードは人体錬成をしたのかな
という感じで、冒頭の『謎』に対しよりいっそう興味が惹かれます。
この『謎』に対する好奇心は非常に強い求心力を持つので、一度その状態にしてしまえば次の話が気になるわけです。
この点で、非常に無駄がない引きになっています。
鋼の錬金術師は、『錬金術』という作品の肝ともいえる設定の説明のためにページを割かざるを得ないので、一話のみで話中の問題を解決することができません。
それでも、しっかりと次に続く引きを作ってあるので、そこまで大きなダメージではないと思います。
むしろ『次が気になる』からこそ、第二話を読ませやすくなっています。
まとめ:鋼の錬金術師の第一話は『起承転結』が驚くほどしっかりしている
こんな感じで『鋼の錬金術師』の第一話をいくつかの要素に分けて時系列に分析しました。
もっとくわしく知りたいという人はぜひ原作漫画を読んでみてください。
鋼の錬金術師の第一話は、とにかく『起承転結』がハッキリしています。
- 起……冒頭シーンと主人公たちの描写
- 承……錬金術と賢者の石についての説明
- 転……悪役を挟んでの小さなどんでん返しの連続
- 結……『人体錬成』と『賢者の石』、そして『鋼の錬金術師』の意味がわかる
正確には完全な『結』には至ってませんが、この一話の中での謎にある程度のケリがつき、その上で次話への興味を誘う引き方になっているので、バランスはとても良いです。
透明.png)
もちろん第一話ですべての伏線を回収し、心地よい読後感を与えたうえで気になる次の話の伏線を匂わせられればこのうえないけど、さすがにそれはページ数的に限界はある。
むしろ、錬金術という小難しい理論のある独自設定を使ったうえで、これだけ起承転結をハッキリさせられているのは十分に脅威です。
個人的には、
- ちゃんと悪役が出てきて
- 主人公たちの動機がしっかり見えて
- 次につながる引きがカッコイイ
このあたりが特に優秀なポイントだと思います。
『鋼の錬金術師』は一話も優秀ですが、総評としてはなんといっても『作品全体を通した構成力が神がかっている』のが一番すごいところなので、気になる方はぜひ読んでみてください。

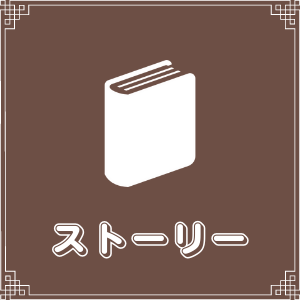



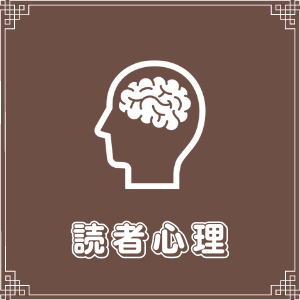



-300x300.png)


